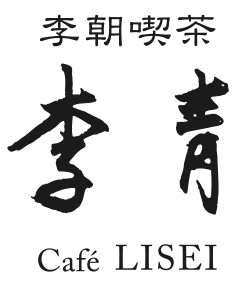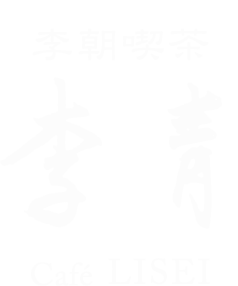李青の薄暗い店内の奥に、明るい光が差し込む小さな庭があります。そこに芽吹く草木は四季折々の姿を見せています。春には店名に由来する李(すもも)、夏は白槿(しろむくげ)や珍珠梅(ちんしばい)、秋は黄色の彼岸花、そして冬も耐え忍ぶ金明竹(きんめいちく)など。鳥が運んでくる種も知らぬ間に育って、開店から30年近く経ったいま、小さくとも豊かな自然界を作り上げています。
李青の庭には「高麗灯籠」(こうらいどうろう)があります。開店する数年前、店主がとある骨董屋でその灯籠と出会いました。あまりに高額のため諦めていたところ、ある日その骨董屋から一本の電話がありました。聞くと、その灯籠を買われた方のところへ運ぶ際、うっかり地面に落とし、一部が欠けてしまったというのです。先方は欠けてしまったものは要らないらしく、あなたのところにお安く譲ります、とのこと。そうしたご縁で、その高麗灯籠は李青の庭に置かれることになりました。
日本では神社でもおなじみの「灯籠」ですが、韓国でこのタイプのものは「石燈」と呼ばれます。もとは寺院の境内や陵墓前に置かれたもので、宮殿や個人宅には見られないものでした。灯籠は仏教と深く関わり、朝鮮半島に仏教が伝来した4世紀末期以降、寺院建立に伴って広く作られるようになったと考えられます。
さて「高麗灯籠」は、呼び名に「高麗」とはあるものの、実際には高麗時代の灯籠ではなく「朝鮮式の灯籠」との意味合いがあります。つまり日本に伝来する高麗灯籠のほとんどは朝鮮時代(1392~1910年)のもの。日本では古来、高句麗・百済・新羅の時代から、朝鮮半島ゆかりの文物を「高麗(こうらい・こま)」と呼び習わしてきました。特に陶磁器や絹織物などの工芸品以外にも地名や寺社仏閣に至るまで、「高麗」の文字は幅広く浸透していて、文化の流れを感じます。
京都の寺や博物館の庭園などでも高麗灯籠を度々見ることがあります。比較的小さく設置しやすい高麗灯籠は、古くから僧侶、茶人や数寄者たちに人気の石造物だったようです。
李青のある河原町今出川から烏丸方面へ西に進むと、同志社大学の今出川キャンパスがあります。その北側に隣接するのが、京都五山の一つとしても有名な臨済宗の相国寺です。境内には承天閣美術館があり、金閣寺や銀閣寺など相国寺派寺院ゆかりの美術工芸品を観ることができます。その敷地の一角に、高麗時代の小さな石造物があります。そこには「もとは鹿苑寺(金閣寺)の庭園に伝わり、大徳寺聚光院にある千利休の墓と同形」との説明文があります。また解説文には「石塔」と書かれていますが、胴部には火窓が備わり、もとは明かりを灯す灯籠の役割を担ったと考えられます。茶人・利休は、小さくとも個性ある高麗の石造物を気に入り、それを真似て自身の墓石としたようです。
ちなみに李青に程近い京都の仙洞御所には「朝鮮灯籠」がありますが、これは日本で作られた朝鮮式の灯籠です。
朝鮮半島の石造物は古くから日本でも珍重され、共通する美意識があったことを感じさせてくれます。